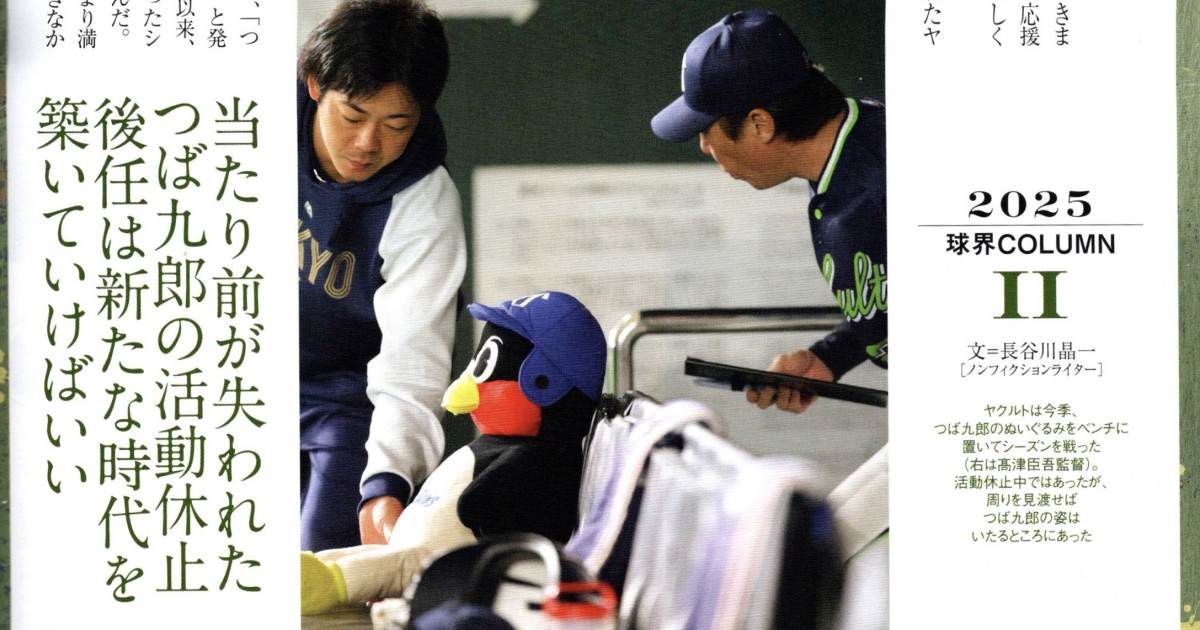髙津監督はどうして、送りバントを多用するのか?
こんにちは。交流戦からの小休止を経て、本日からペナントレース再開となります。本日、アルファポリス・「髙津流マネジメント2025」の最新回が公開されました。交流戦全日程を終えて、この間に考えていたこと、どんな思いだったのかを中心に尋ねています。
さて、今回のタイトルは「交流戦、屈辱の最下位——最悪のチーム状況で指揮官はどう戦ったのか」と題されています。詳しくは本文をご覧いただくとして、3ページ目に「なぜ、送りバントを多用するのか、その理由とは?」と題された一節があります。試合を見ていて、「えっ、ここでバント?」とか、「ここ最近好調なのだから、打たせてもいいのでは?」と感じることがしばしばあります。
SNSを見ていても同様の声は多く見られ、ファンの中にもフラストレーションが溜まっていることが伝わってきます。僕自身の考えで言えば、「ここまで負けているのだから、目の前の1点よりも、その選手の将来性に投資してほしい」という思いもあります。
一方で、「これだけ悔しい現実を目の当たりにしているのだから、ガムシャラに勝利を目指してほしい」という思い、そして「そのためには送りバントもやむなし」という思いもあります。これまで、何度か「どうしてバントを多用するのですか?」と、監督に尋ねてきました。
「不動の四番である村上宗隆が欠け、塩見泰隆、長岡秀樹が故障したことで、圧倒的に得点力が落ちている現状だからこそ、とにかく得点圏に走者を進め、目の前の1点を取りにいく」
監督の口からは、そんな言葉が聞かれました。けれども、すでに65試合を消化した今、改めてその思いについて尋ねてみると、僕の想像以上に監督は多弁に、その理由、そして心に秘めていることを話してくれました。印象に残ったのは、こんなセリフでした。
《今のチーム事情を考えると、僕の理想というのは、例えば4点を奪うとしたら、「0、2、0、2」で4点を取るよりも、「1、1、1、1」の4点を狙っています。》
そして、監督はその具体例として、こう言いました。
《バファローズとの試合で小川(泰弘)にスクイズさせた場面がありましたよね。》
6月20日のオリックス・バファローズとの初戦。2回裏、2対3と1点差に追いつき、一死二、三塁の場面で、打者の小川投手にスクイズを命じたシーンです。監督インタビューを続けていると、しばしばこんなことが起こります。ある具体的な場面を例に挙げて、その意図の解説が始まるのです。